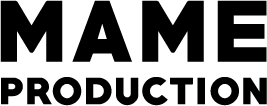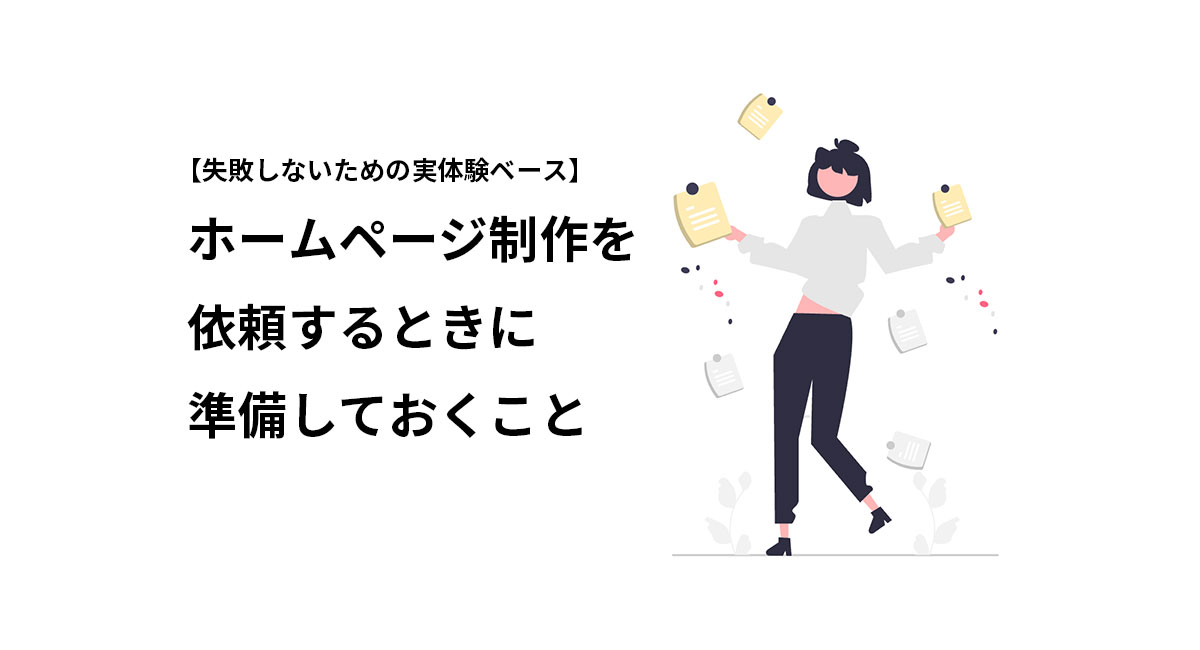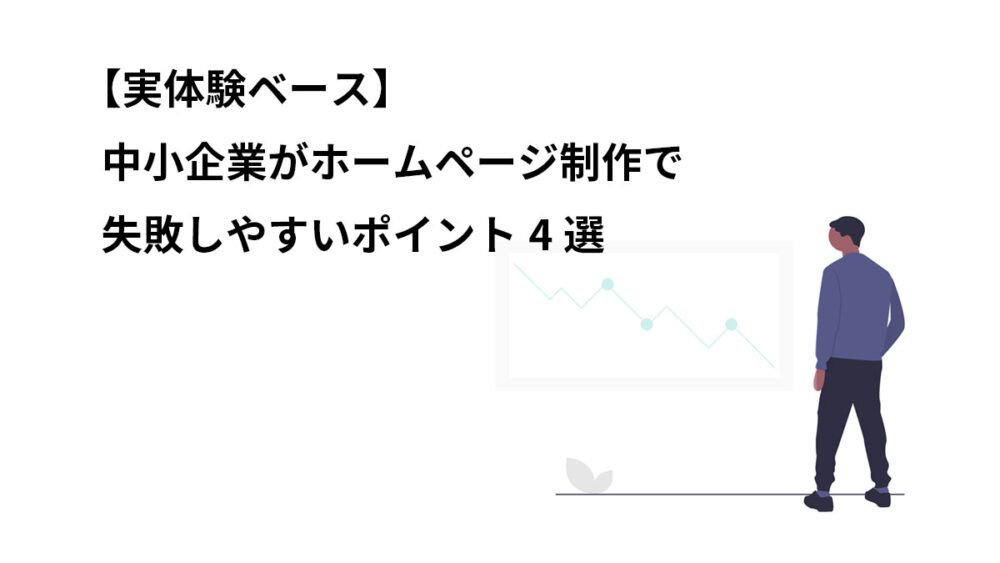
「せっかくお金と時間をかけたのに、できあがったホームページに満足できない…。」
中小企業や個人事業主のサイト制作で、よく耳にする悩みです。
原因は制作会社やデザイナーのスキル不足だけでなく、発注側の準備や意思決定の進め方にもあることが多い。フリーランスとしていろいろな案件に関わってきた中で、「あ、これ失敗パターンだな…」と感じた場面を4つ紹介します。あわせて、どうすれば回避できるのかもまとめました。
これからホームページ制作やリニューアルを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
※全体の流れから失敗しない発注方法まで体系的に知りたい方は、
「ホームページ制作発注 完全ガイド」も合わせてご覧ください。
失敗1|コンセプトが定まらないとホームページ制作は失敗する
「とりあえずカッコよく」「今の流行に合わせたい」といった理由だけで進めてしまうと、誰にも響かない“平均点のサイト”になりがちです。
- 誰に見てほしいのか(ターゲット)
- どんな行動をしてほしいのか(価値提案・CTA)
- 競合とどう違うのか(差別化)
これらがあいまいだと、デザインも構成もブレてしまいます。
経験談
明確なターゲット像がないまま、どんなデザインにしたいかという話題を進めてしまう。
競合他社のホームページを見せながら、「こんな感じで」と曖昧なまま制作が進んでしまう。
回避策
最初にワンページの戦略メモを作る。
誰に向けたホームページなのか、なぜ貴社の商品が選ばれるのか、そしてホームページ上でのゴールは何か。
ポイントは、完璧な戦略資料ではなく「サイト制作の判断基準」になるメモにすること。
これがあると、デザインの方向性や文章のトーン、ページ構成で迷わなくなります。
失敗2|社長の考えがスタッフに伝わらないままホームページ制作を進めてしまう
リニューアルの現場でありがちなのが、社長の考えがスタッフにちゃんと伝わっていないまま進んでしまうケースです。
「今回のリニューアルは何のため?」
「新しいサイトでどんな成果を目指す?」
このあたりが共有されていないと、現場は方向性が分からず、更新や運用が行き当たりばったりになります。
ところが現実には、目的を示さないまま社長が細かな文章だけ自分で書いてみたり、逆に「運用はスタッフに任せるから」と丸投げしてしまうことも少なくありません。
これでは当然、うまくいきません。
トップがゴールを示さずに細部をコントロールしようとすると、スタッフは「どの方向に向かって記事を書けばいいのか」「何を優先すべきか」が分からず、結局サイトが止まってしまうのです。
回避策
- 社長自身が「リニューアルの目的」と「どう変えたいか」を短くまとめる
- 打ち合わせの度に、「リニューアルの目的」などを共有する
失敗3|自社の強み・弱みを整理しないとホームページ制作で差別化できない
自社の強みと弱みを言語化できていないと、他社と差別化ができずに価格競争に巻き込まれてしまいます。
社内の人にとっては当たり前すぎて気にも留めないことが、お客さんからは素晴らしいことに見えることが多々あります。
経験談
とある宿泊施設のサイトリニューアルでは、料理と温泉を強みに据えたいと要望されました。
しかし、有名温泉街でしたので、どこの宿泊施設も温泉を強みとしており、ユニークなアピールポイントにはなりませんでした。
回避策
- 既存顧客に簡単なアンケートを実施(選んだ理由/良かった点/改善点)
- Googleなどの口コミに目を通し、お客さんの意見を汲み取る
失敗4|デザインを好みで判断するとホームページ制作の成果が出にくい
「青は嫌いだから使わない」「丸文字は苦手だからやめて」…こうした好みだけの判断でデザインを進めると、ユーザーの体験や成果が置き去りになります。
経験談
デザインの好みを優先した結果、既存顧客から評価されていたポイントを外してしまうデザインが採用されてしまいました。
「見た目はスッキリしたけれど、他社との違いが伝わらなくなった」「会社らしさが消えてしまった」といった声もあり、成果につながりにくいサイトになってしまいました。
回避策
- ユーザー目線で考える
- 数字で判断する(GA4のイベント計測やCVRを見る)
- 「好み」と理解したうえで、相手に伝える
まとめ
ホームページ制作の失敗は、制作段階よりも準備や意思決定の段階で生まれることが多いです。
- コンセプトを定める
- ゴールをスタッフまで共有する
- 自社の強み・弱みを整理する
- デザインは好みではなくユーザー目線で判断する
下記の記事もぜひご覧ください
失敗しないために、実際の事例を参考にしてください
ホームページの運用改善に興味がある方はこちらもご覧ください
運用改善プランを見る