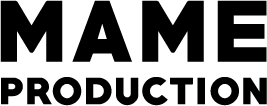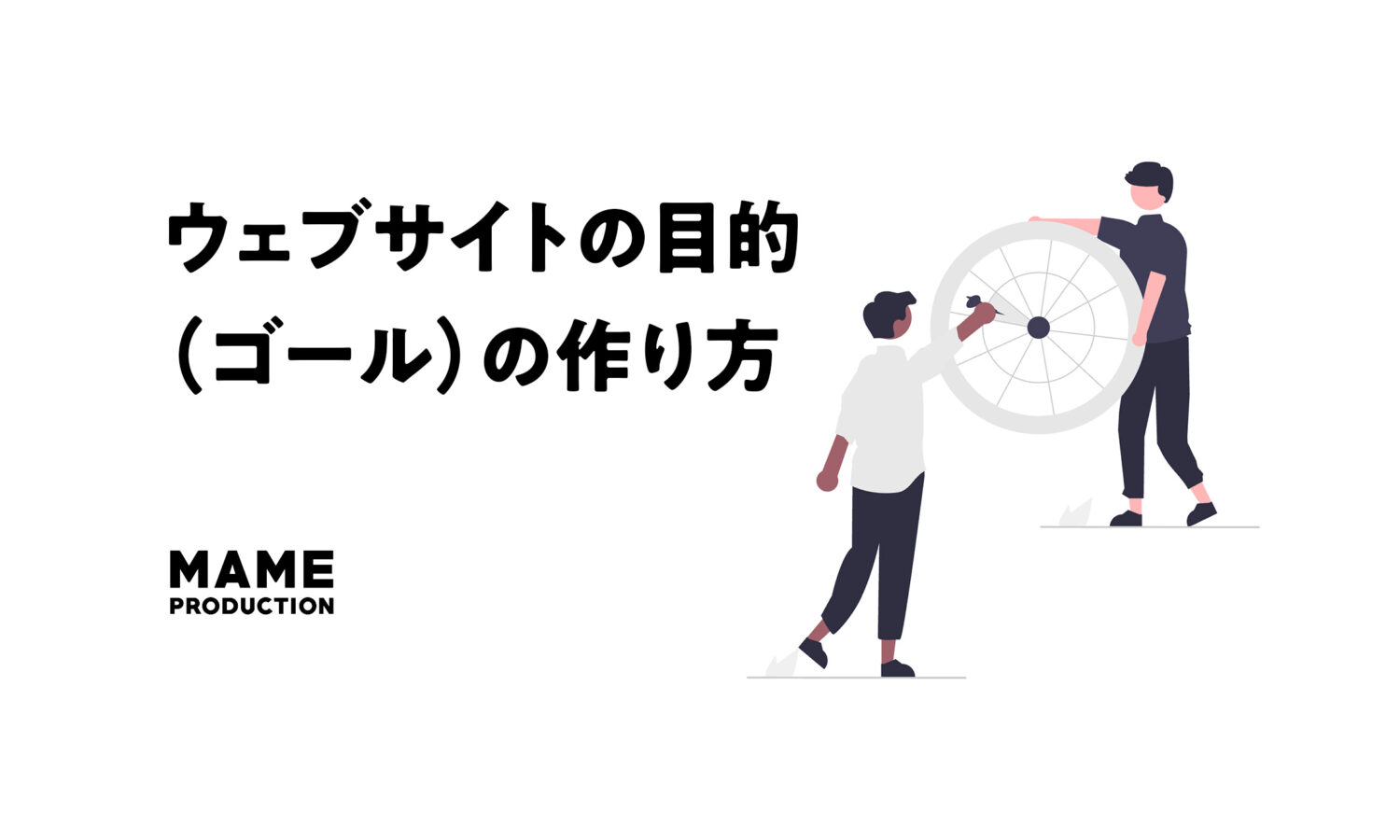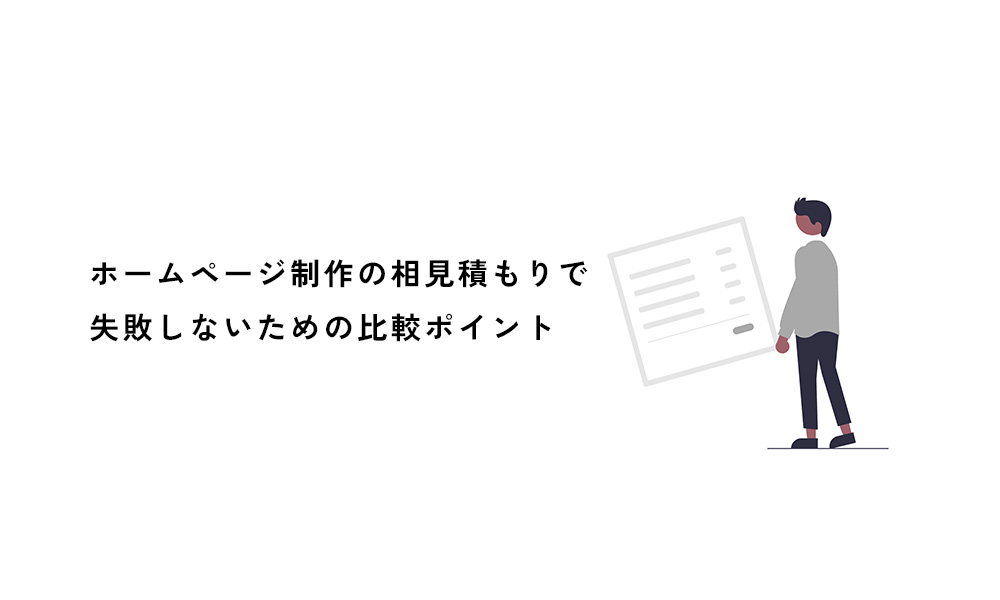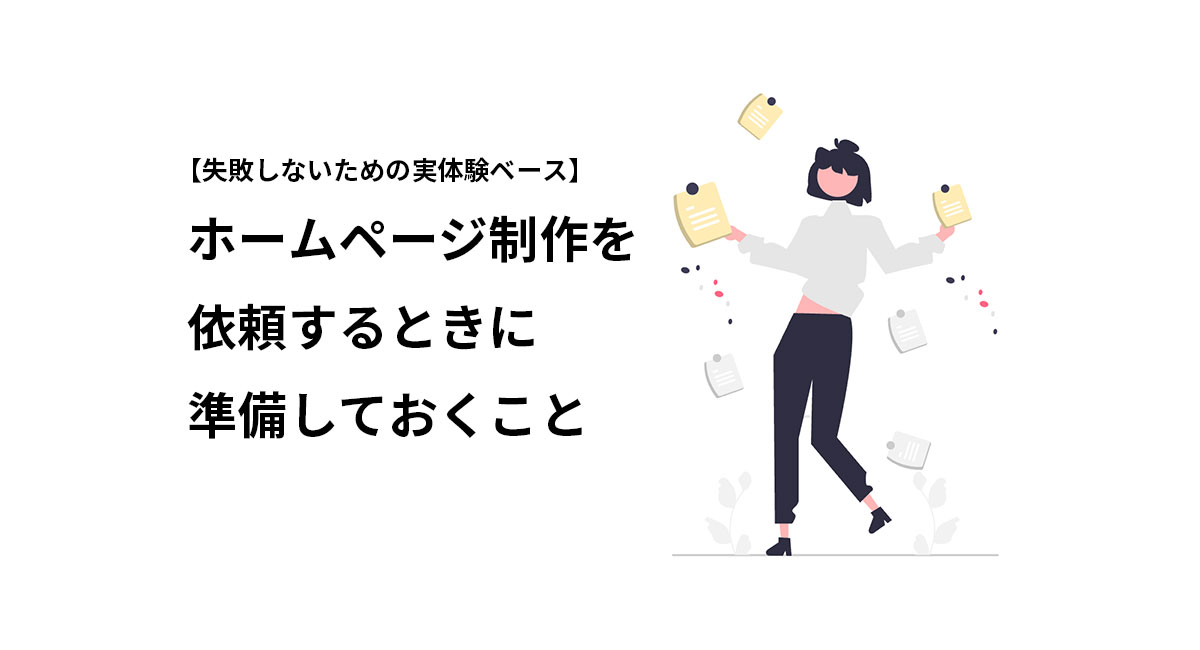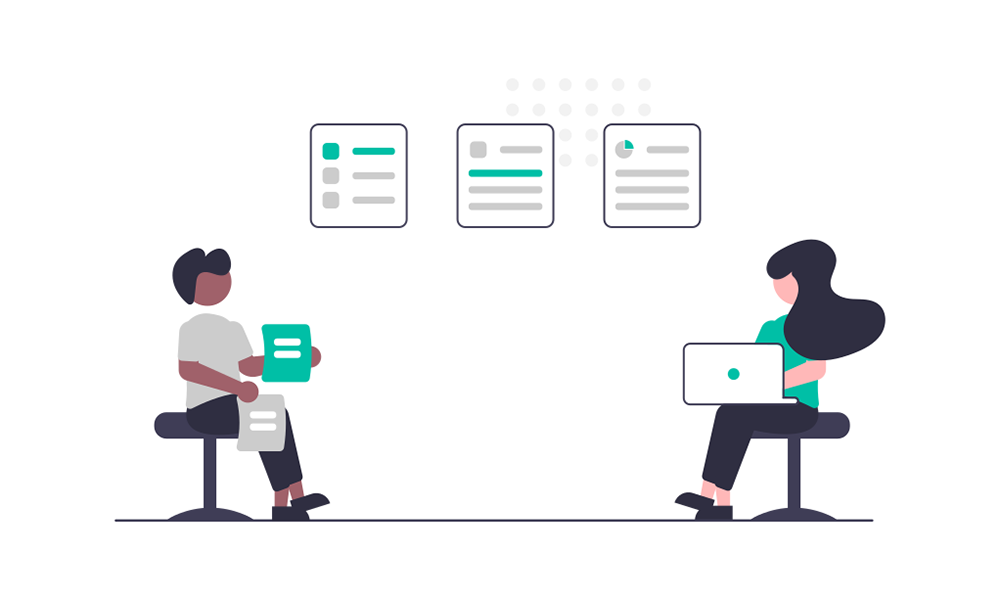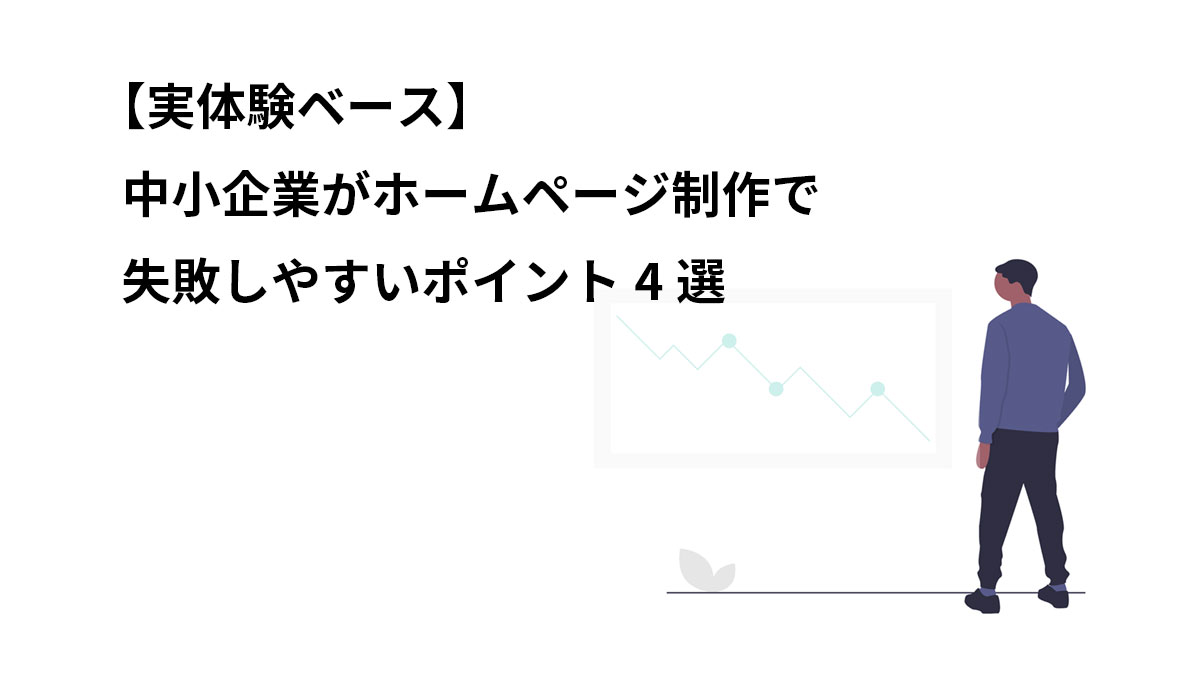ホームページを発注しようと思っても、費用の相場や、どこに頼むべきか、何を準備すればいいのか…最初は分からないことばかりだと思います。
そう感じるのは自然なことで、発注される多くの方が同じように迷っています。
- この見積は高いのか安いのか分からない
- 制作会社とフリーランス、どちらが合っているのか判断できない
- トラブルなく進められるか心配
- どのくらい自分が準備する必要があるのか不明
こうした不安は、誰にでもあります。
でも安心してください。
この記事では、ホームページ制作の発注で迷いやすいポイントを、必要なところだけ分かりやすくまとめています。
費用の目安、事前準備、制作の流れ、良い制作会社やフリーランスの選び方まで、この1本を読めば全体像がつかめるようになっています。
はじめての方でも、落ち着いて発注先を選べるように作ったガイドです。どうぞ安心して読み進めてください。
1. 発注前に知っておきたい基本
【重要】どんなホームページが必要なのか、「目的」を考える
まず決めるべきなのは、サイトを作る目的です。
- 問い合わせを増やしたい
- 店舗への来店を増やしたい
- 会社の信頼感を上げたい
- 採用応募を増やしたい
- 既存顧客のフォロー目的
- ブランドづくり
目的が曖昧なまま進むと、制作途中で軸がブレて混乱し始めます。
最初に制作側と目的を共有しておくことで、全体の流れがスムーズになります。
2. ホームページ制作の費用相場
ホームページの制作費は、会社によって異なります。
また、制作会社とフリーランスでは、金額が大きな差が出てきます。
規模別のざっくり相場
| サイト規模・種類 | フリーランスの相場 | 制作会社の相場 |
|---|---|---|
| 5〜7ページ | 20〜40万円 | 40〜70万円 |
| 10〜15ページ | 50〜100万円 | 100〜150万円 |
| LP(1ページ) | 10〜30万円 | 20〜50万円 |
| WordPress構築 | 30〜100万円 | 100万円〜 |
制作会社は、同じサイト規模でもフリーランスの約2〜3倍の費用になるケースが多いです。
ただし、金額だけで比較するのではなく、同じ予算でどこまで対応してくれるかを見ることが大切です。
■ 金額の差は何?
理由は様々ですので、A社とB社の単価を比較してもあまり意味がありません。
制作会社とフリーランスの差ということで言えば、下記のようなことで金額に差が出てくると考えられます。
- 責任の範囲
- 担当者の人数
- 設計段階の作り込み
- デザインの作り込み
- 写真・文章のサポート
- 運用サポートの範囲
■ 値段で判断するのではなく、予算内でどこまで対応してくれるか、で判断する
費用は高い・安いだけで判断できません。
大切なのは「同じ予算で、どこまで対応してくれるか」という点です。
見積書を見るときは、金額よりも範囲と内容を基準に比較しましょう。
3. 制作会社とフリーランスのどちらに依頼すべきか
ホームページ制作の依頼先は、制作会社とフリーランスの2つがあります。
違いは主に、体制・費用・進め方の三つです。
■ 制作会社の特徴
- 複数の担当者が関わるため、体制が安定している
- 大規模サイトや複雑な機能にも対応しやすい
- 費用は高めになりやすい
- コミュニケーションの段階が多め
■ フリーランスの特徴
- 本人と直接やり取りできるため、進行がスムーズ
- 費用を抑えやすい
- 小〜中規模サイトに向いている
- 一人で対応するため、納期や長期運用は負荷が集中しやすい
■ 選ぶ基準
- 予算を抑えたい → フリーランス
- 運用やサポートまで任せたい → 制作会社
- 担当者と直接やり取りしたい → フリーランス
- 安心できる体制を重視したい → 制作会社
目的と必要なサポート量によって、どちらが合うかが自然に決まります。
4. 良い制作会社(または良いフリーランス)の選び方
■ 実績が自分の業界や目的に近いか
制作実績を見るときは、数よりも、あなたの案件と性質が近い制作を経験しているか が重要です。
チェックすべき点
- 同じ業界・同じ商材を扱った制作例があるか
- 自分のサイト構成に近いボリュームの実績があるか
- 課題解決の視点を持った実績説明ができるか
目的の近い実績があるほど、打ち合わせでのズレが少なくなります。
■ 相談時のコミュニケーションの質
発注前の会話で、相手の実力と姿勢、そして相性がわかるはずです。
見るべきポイント
- 依頼内容だけでなく、目的やゴールを把握してくれてるか
- わからないことは、しっかり質問してくれるか
- 不足している要件など、的確に指摘や質問してくれるか
- 専門用語だけで話さず、わかりやすい説明があるか
話していて「理解されている」と感じるかどうかが、最も信頼できる判断材料です。
■ 提案資料や見積書などのドキュメントの質が高いか
提出される書類は、制作者の思考の質がそのまま出ます。
金額よりも、作業内容が明確に書かれているかを基準に判断してください。
チェックすべき点
- PDFや資料のレイアウトが整っていて、読みやすい
- 作業範囲が明確で、曖昧な表現が少ない
- 納品物が言語化されている(ワイヤー、デザイン、テキスト、CMS設定など)
- 追加料金が発生する条件が明記されている
書類が雑な制作者は、作業も雑です。
逆に、ドキュメントが丁寧な制作者は、制作も安定しやすく、コミュニケーションが明確です。
5. 発注前に準備しておくとスムーズになるもの
■ 最低限そろえておく情報
- サイトを作る目的
- 主なターゲット(誰に見てほしい?)
- 競合や参考サイト
- サイトマップ(ページ数の目安になる)
- 予算
- 公開希望日
- ドメインやサーバーの情報(なければ新規契約する)
■ 企業ロゴ・写真・文章
- ロゴデータ
- ホームページで使えそうな写真
- パンフレットなど(企業のイメージが伝わる)
完璧でなくても構いませんが、早めに揃えておくと進行がスムーズになります。
6. 制作開始から公開までの流れ
実際のホームページ制作は、下記のような工程で進みます。
- オリエンテーション
- 目標設定
- 設計(ワイヤーフレーム・構成案)
- デザイン制作
- コーディング・WordPress構築
- 公開前のテスト
- 公開
- 公開後サポート
どの工程ももちろん大事ですが、発注者の方に特に意識したいのは、下記2点。
- オリエンテーション
- 目標設定
オリエンテーションでは、デザインなど「見た目」の話をしてしまいがちですが、それよりも会社内部のことやホームページ制作の背景といった、バックボーンについて詳しく話すことを心がけてみてください。
7. よくあるトラブルと防ぎ方
ホームページ制作では、発注者と制作者の認識のズレから、思わぬトラブルが起こることがあります。内容は複雑そうに見えますが、実際によくあるトラブルは決まったパターンに収まります。
事前にポイントを押さえておけば、ほとんどの問題は回避できます。
■ 仕上がりのイメージが違う
もっとも多いのが、完成したデザインや構成が「思っていたものと違う」というケースです。
原因のほとんどは、初期のすり合わせ不足 です。
【防ぐ方法】
- 初回相談の段階で、相手が目的やターゲットを言語化してくれるか確認する
- デザインに入る前に、必ずワイヤー(構成案)を共有してもらう
- 実績の中から、自分の目的に近いものを選んで説明してもらう
制作前の認識合わせが丁寧な制作者ほど、ズレが起きにくくなります。
■ 追加費用が予想以上にかかる
見積は安かったのに、ふたを開けたら追加料金がどんどん発生するパターンです。
作業範囲や仕様が曖昧なまま契約してしまうことが原因 です。
【防ぐ方法】
- 見積書・提案資料のドキュメントの質をチェックする
- 作業範囲(ページ数、デザイン数、対応範囲)を明文化してもらう
- どのケースで追加料金が発生するか、事前に確認する
ドキュメントが丁寧な制作者ほど、追加費用のトラブルは起きません。
■ 納期が遅れる
「忙しくて手が回らない」「確認が遅れて進まなかった」など、理由はさまざまですが、スケジュール管理の甘さ から発生します。
【防ぐ方法】
- 制作者にスケジュール表を出してもらう
- 制作者側から、あなたの提出物(テキスト・写真等)の期限を提示してくれるか確認
進行管理をきちんと説明できる制作者は、遅延も起こりにくいです。
■ 納品後のサポートが受けられない
納品されたあとで修正や更新をお願いしたいのに、対応してもらえない…というケースです。
多くは 運用や保守の話を事前にしていないこと に原因があります。
【防ぐ方法】
- 公開後の修正について、対応期間や費用など確認しておく。
- 保守・運用プランの有無を聞く
- 軽微修正の対応スピードを確認しておく
制作後の関係まで見据えている制作者ほど、長期的に安心して任せられます。
■ 瑕疵(不具合)があるのに対応してもらえない
リンク切れ、レイアウト崩れ、フォームが動かないなど、納品物に不具合がある場合の対応トラブルです。
瑕疵対応の期間や範囲を定めていないと揉めがち です。
【防ぐ方法】
- 瑕疵対応の期間(例:納品後30日)を事前に明確にする
- どこまでが瑕疵で、どこからが追加作業か説明してもらう
- テスト環境・チェック体制について質問する
きちんとテストを実施している制作者は、そもそもの不具合も少なくなります。
【重要】契約書は必ず交わしましょう
上で挙げたトラブルの多くは、契約書があれば防げるもの です。
作業範囲・納期・瑕疵対応・追加費用の条件など、重要な内容は必ず契約書に盛り込みましょう。
8. 公開後の運用について
ホームページは、公開して終わりではありません。
成果を出すためには、公開後の運用が欠かせません。主に必要になるのは次の三つです。
■ 定期的な更新
お知らせ、ブログ、写真の差し替えなど、情報を最新に保つことが信頼性につながります。
更新が止まると問い合わせも減りやすくなります。
■ メンテナンスとセキュリティ
WordPressの場合、プラグイン更新やバックアップなどの管理が必要です。
放置すると不具合やセキュリティリスクが発生する可能性があります。
■ アクセス解析と改善
Google AnalyticsやSearch Consoleを使い、ページの閲覧データや検索順位を定期的に確認することで、改善の方向性が見えてきます。
【重要】運用を外注するかどうか
更新頻度が高い場合や、社内に担当がいない場合は、制作会社やフリーランスの運用プランを利用するのも有効です。作業内容によって月額の相場は変動します。
公開後の運用内容は、事前に確認しておくと安心です。
最後に
ホームページ制作は、業者選びや相場の理解、事前準備など、考えることが多く不安になりやすい分野です。
しかし、目的を明確にし、信頼できる制作者と丁寧に認識を合わせて進めれば、制作は必ずスムーズになります。
今回紹介したポイントを押さえておけば、発注の失敗はほとんど防げます。
焦らず、あなたのビジネスをしっかり理解してくれるパートナーを選んでください。
ホームページの運用改善に興味がある方はこちらもご覧ください
運用改善プランを見る